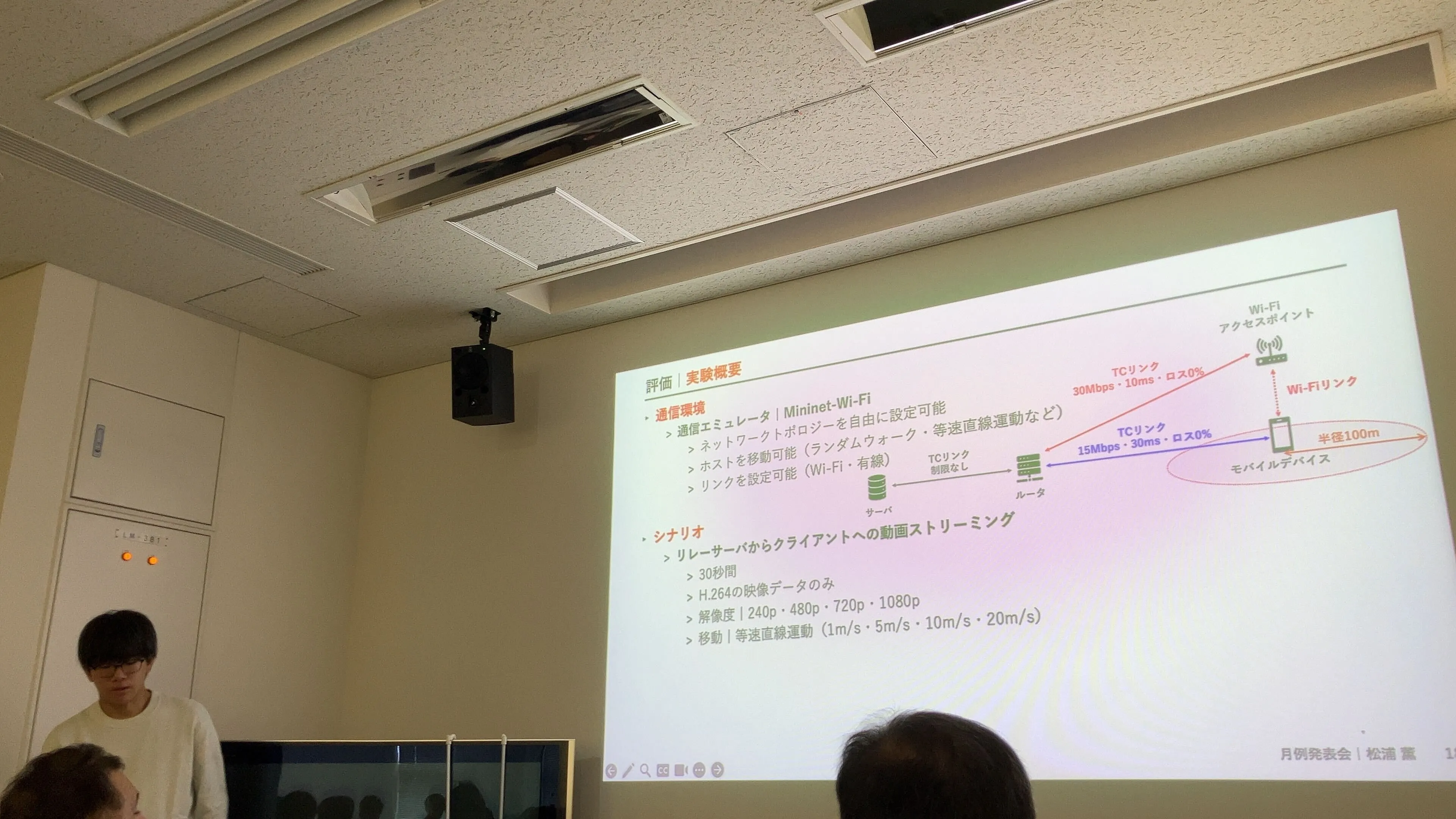2025年9月28日に開催された「2025年度 情報処理学会関西支部 支部大会」において,岩井駿人(M2)が以下のタイトルで発表を行いました.
協調型自動運転のための組込みRTOSによる時空間グリッド予約システムの実装と評価

人工知能やセンサ技術の進化により,自動運転技術は,交通事故の削減や渋滞緩和など,多くの社会課題を解決する手段として注目を集めている.このような背景のもと,これまでの自動運転の研究では,車両に搭載されたセンサやカメラ,LiDAR,レーダ,GPSなどを用いて周囲の環境を認識し,経路計画から運転操作まですべて車両自身が行う「自律型自動運転(Autonomous Driving)」が中心的な研究対象となってきた.自律型自動運転の利点は,外部との通信やインフラへの依存を最小限に抑え,車両自身が判断と制御を行うことで走行できる点である.また,実証実験や社会実装も目指されている.しかしながら,自律型自動運転には技術的な課題が存在する.例えば,車両に搭載されているセンサによる認識範囲は限られており,見通しの悪い交差点や遮蔽物の裏側など,車両自身では認識できない情報に基づく判断が困難であり,誤認識による事故が発生する可能性がある.
このような背景により,近年では「協調型自動運転(Cooperative Automated Driving)」が新たなアプローチとして注目されている.協調型自動運転とは,自車両のセンサ情報に加えて,他車両や道路インフラとリアルタイムに情報を共有し,連携して走行を行う方式である.また,これらの情報を統合することにより,複数の車両や周辺の情報を考慮した,全車両の走行経路の最適化を行う走行調停ができるため,交差点の通過や合流などの複雑な場面でも,安全かつスムーズな走行が可能となる.
協調型自動運転を実現するための技術基盤としては,「V2X(Vehicle-to-Everything)通信」がある.V2X通信は,図1に示すように車両間で直接通信を行うV2V(Vehicle-to-Vehicle)通信,信号機などの道路設備と通信を行うV2I(Vehicle-to-Infrastructure)通信,ネットワークを介したV2N(Vehicle-to-Network)通信,および歩行者と車両との間で通信を行うV2P(Vehicle-to-Pedestrian)通信から構成されており,それぞれの通信手段を通して多様な情報を相互にやり取りすることができる.これにより,車両は自らの認識限界を補い,より広範囲かつ高精度な環境把握と意思決定を行うことが可能となる.
一方で,協調型自動運転の実現には新たな技術的課題も存在する.複数の車両が同時に通信を行い,意思決定と走行制御を協調させる必要があるため,通信量や計算量の増大の問題が発生する.これらの課題を克服するには,通信・処理の効率性を保ちつつ,通信資源や計算資源を明示的に調整できるような仕組みが求められる.
本研究では,協調型自動運転における通信および処理負荷を軽減するために,プリエンプティブな優先度ベーススケジューリング方式の組込みRTOS(Real-Time Operating System)を利用して,複数の自動運転車両がリアルタイムに走行調停を行うシステムを構築する.RTOSとは,決められた時間内にタスクを確実に完了させることを保証するリアルタイム性を備えたOSであり,タスクの優先度に応じて即時に処理を切り替えることが可能である.本研究では,協調型自動運転において走行制御や通信など優先度の異なる処理を安全かつ確実に実行する必要があることから,プリエンプティブな優先度ベーススケジューリング方式を採用している.RTOS上に時空間グリッド予約システムを実装し,各車両の走行制御を優先度に応じて動的に行うことで,即応性と安定性の両立を図る.また,計算量を最小限に抑えつつ,衝突回避や走行調停が確実に行えるよう設計する.